ここから本文です。
ホーム > 教育・文化・スポーツ > 教育・健全育成 > 学校教育 > 生徒指導(いじめ・不登校児童生徒支援) > 教職員用「児童生徒の自殺防止対策啓発リーフレット」児童生徒を自殺の危機から救うために
教職員用「児童生徒の自殺防止対策啓発リーフレット」児童生徒を自殺の危機から救うために
県教育委員会では、自殺予防に関する県の取組及び具体的な教職員による予防対策や児童生徒への予防教育、さらに自殺が起きてしまったときの対応等について学校現場での利用を想定した啓発資料を作成しました。
各学校等でこのリーフレットを研修等で御活用自殺予防教育を推進してください。
1.児童生徒の自殺は深刻な問題です。
児童生徒の自殺者数の推移【全国】
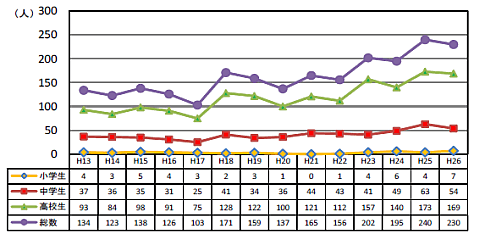
(文部科学省「平成26年度児童生徒の問題行動等生徒指導上の諸問題に関する調査」より)
- ※1年度(4~3月)集計。
- ※2平成17年度までは、公立学校のみの数値。平成18年度からは、国公私立学校の数値。
- ※3平成25年度からは、高等学校通信制課程を調査対象に含めている。
- ※4自殺者数の報告について、平成24年度からは、学校が警察により自殺と判断されたものを把握した場合も計上している。
児童生徒の自殺は、一般に考えられている以上に深刻です。「平成26年人口動態統計の概況」(厚生労働省)によると、10代の死因は「自殺」が1位となっています。
2.どのような子供に自殺の危険が迫っているのでしょう。
自殺の危険因子と子供に現れる自殺直前のサイン
10代の自殺は原因が特定されず、衝動的に行うという例もあります。しかし、次のような特徴を数多く認める子供には潜在的に自殺の危険性が高いと考えることができます。
- 自殺未遂・自傷行為(リストカット、薬を余分に服用するなど)
- 心の病(うつ病、統合失調症、パーソナリティ障害、薬物乱用、摂食障害など)
- 安心感の持てない家庭環境(虐待、親の養育態度の歪み、頻繁な転居、兄弟姉妹間の葛藤など)
- 独特の性格傾向(未熟・依存的、衝動的、極端な完全癖、抑うつ的、反社会的など)
- 喪失体験(離別、死別、失恋、病気、けが、急激な学力低下、予想外の失敗など)
- 孤立感(仲間からのいじめ、無視など)
- 安全や健康を守れない傾向(事故や怪我を繰り返す)
これらの特徴を持つ子供に、下にあるような普段と違った顕著な行動の変化が現れた場合には、自殺直前のサインとしてとらえる必要があります。
自殺直前のサイン(例)
- 自殺のほのめかし・自殺計画の具体化・自傷行為・行動、性格、身なりの突然の変化
- 怪我を繰り返す傾向・アルコールや薬物の乱用・重要な人の最近の自殺・家出
- 別れの用意(整理整頓、大切なものをあげる)・最近の喪失体験
このほかにも・・・
- これまでに関心のあった事柄に対して興味を失う・注意が集中できなくなる
- いつもならできるような課題が達成できない・成績が急に落ちる
- 不安やイライラが増し、落ち着きがなくなる・投げやりな態度が目立つ
- 身だしなみを気にしなくなる・健康や自己管理がおろそかになる
- 不眠、食欲不振、体重減少などのさまざまな身体の不調を訴える・学校に通わなくなる
- 自分より年下の子供や動物を虐待する・友人との交際をやめて、引きこもりがちになる
- 家出や放浪をする・乱れた性行動に及ぶ
- 自殺にとらわれ、自殺についての文章を書いたり、自殺についての絵を描いたりする
- 過度に危険な行為に及び、実際に大怪我をするなど
自殺直前のサインを敏感に感じ取れるよう、日頃から子供の様子を十分把握しましょう。また、子供は自分の思いに気付いてほしいと思っています。変化を感じたら、「どうしたの?」と声をかけてあげましょう。
信頼感のない人間関係では、子供は心のSOSを出せません。子供の中に「あの先生なら助けてくれる」という思いを持てるよう、信頼関係づくりに努めるようにしましょう。
また、教職員一人の目では子供の変化に気付かないことがあります。日頃から教職員同士で子供の様子について情報交換するように心掛けましょう。
3.子供から「死にたい」と訴えられたり、子供の自殺の危険性を感じ取ったりしたら・・・
| 「大丈夫、がんばれば元気になる」など安易に励ましたり、「死ぬなんて馬鹿なことを考えるな」などと叱ったりしては、かえって心が閉ざされてしまいます。 |
TALKの原則
|
対応の留意点、一人で抱え込まず、必ずチームで対応することが重要です。>
チームで対応することは、多くの目で見守ることにより子供への理解を深めるとともに、共通理解を
得ることで、教師自身の不安感の軽減にもつながります。
急に子供との関係を切らない
自殺の危険の高い子供は、しがみつくように依存してくることも少なくありません。関わりに疲れてしまい、急に関係を切ってしまうといった態度は、子供を不安にさせます。
「秘密にしてほしい」という子供への対応
打ち明けられた教師だけで見守ることなく、守秘義務の原則に立ちながら、どのように校内で連携できるか、共通理解を図ることができるかが大きな鍵となります。
手首自傷(リストカット)への対応
将来起こるかもしれない自殺の危険を示すサインととらえ、本人の苦しい気持ちを認めるような姿勢で関わります。できれば医療機関につなげ、情報を共有し、継続的に関われるようにします。
※詳しくは文部科学省資料「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」第2章を参照してください。
4.自殺の予防は、学校生活の充実から(日頃の教育活動を通して)
児童生徒の自殺は多様かつ複合的な要因が考えられます。内閣府・警察庁の調査によると、児童生徒の自殺の原因・動機のうち、約4割は「学校問題」が関連しているそうです。子供たちは、仲間との人間関係づくりや学習面、進路の面等に多く悩みを抱えています。
子供の1日の生活のうち、多くの部分を学校生活が占めています。だからこそ、学校生活を子供たちにとって充実したものにしていくことが大切です。
教職員は、学校を、子供にとって安心できる、自己存在感や充実感を感じられるといった、落ち着ける居場所にしていく役割を担っています。また、生徒指導の機能を生かした授業を心掛けるなど、子供一人一人が主体的に取り組む協同的な活動の場を通して、子供自身が絆を感じ取れ、作れるよう、支援していくことも大切です。
教職員による居場所づくりと、子供の絆づくりが相互に機能していくことにより、子供たちが安心して学校生活が送れるようになり、それが自殺の予防にもつながります。教職員による居場所づくりと、子供の絆づくりが相互に機能していくことにより、子供たちが安心して学校生活が送れるようになり、それが自殺の予防にもつながります。
5.すべての児童生徒を対象とした自殺予防教育はどのように進めていけばよいのでしょうか。
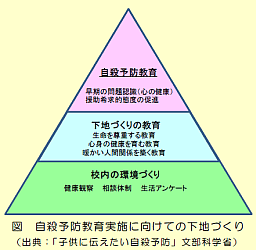
平成26年7月に文部科学省より「子供に伝えたい自殺予防(学校における自殺予防教育導入の手引き」が発行されました。
自殺予防教育を行うことは「寝た子を起こす」という不安が強いのではという見方がある中、文部科学省は
- (1)生涯を通じたメンタルヘルスの基礎づくり、
- (2)友人の危機に適切に対処できる「ゲートキーパー」養成、
- (3)自殺に関する誤った情報・不適切な情報や思い込みから子供を守る、
という視点で自殺予防教育の必要性を挙げています。
とはいえ、自殺予防教育は大変デリケートな内容であり、難しいものです。
ここに示した内容は一部ですので、文部科学省の資料を必ず熟読し、内容を十分に理解した上で、組織的に取り組むようにしてください。
(1)自殺予防教育を実施する上での前提条件
自殺予防教育を実施する以上、次の3つの前提条件を適切に整える必要があります。条件の整わない状況で早急に取り組むのは避けてください。
実施前に関係者間で合意を形成しておきます。
なぜ子供を直接対象とする自殺予防教育が必要なのか、教職員・保護者・地域の関係機関等の関係者が十分に話し合い、その内容を理解して合意に達しておかなければなりません。
当然のことながら、教職員自身が不安なまま自殺予防教育を始めることは無謀です。学校全体で必要性や意味を共有し、一体となって取り組むことが重要です。そのためには学校の実態に応じた校内実施組織を立ち上げ、教職員研修の実施計画や授業の事前準備から授業後のフォローアップまでの計画、そして、子供対象の自殺予防教育プログラムの検討を行っていきます。
保護者に対しては、保護者対象の研修を行い、必要性や内容について共有するとともに、自殺予防教育の実施について保護者が持つ不安に対して、学校として誠実に対応する姿勢を見せる必要があります。
地域の関係機関に対しては、日頃から協力関係を築いておき、自殺予防教育への理解・協力を求めておきます。
適切な教育内容を準備します。
自殺をおとしめたり、逆に美化したりするような扱いは避け、自殺の実態を中立的な立場で示すことで、データそのものが事態の深刻さを語るように伝えていきます。自殺の危機を早い段階で気付き、適切な対応をとることによって、自殺は予防可能であることを理解できるようにします。
ハイリスクの子供をフォローアップします。
身近な人の自殺を経験した子供が存在する可能性も含め、授業実施前後のアンケートや面談等を通して気付いたハイリスクの子供については、学校内でどう支えるのか、保護者に誰がどのようにリスクを説明するのか、極めて危険性の高い子供には専門家による治療等をどのように導入するのかといった点について、前もって話し合っておきます。
(2)自殺予防教育の目標及び自殺予防教育プログラムの内容
目標
- 早期の問題認識
(心の健康状態への気付き) - 援助希求的態度の育成
(援助希求的態度とは、問題や悩みを抱えて自分では解決しきれないと感じたときに、誰かに相談したり、助けを求めたりしようとする態度のことです。)
目標を達成するために、実際に授業をするにあたっては、実態に応じて次のような内容を組み入れていきます。
- 自殺の深刻な実態を知る。
- 心の危機のサインを理解する。
- 心の危機に陥った自分自身や友人への関わり方を学ぶ。
- 地域の援助機関を知る。
(3)実施前の留意点
下地づくりをしっかりと
日頃、実施している教育活動の中には、自殺予防教育の下地づくりとなる内容(右図参照)が多く含まれています。また、下地づくりをするには、校内の環境づくりも大切です。日頃からの教育活動を充実させ、子供たちの心を育てていく必要があります。
学級集団レベル、個人レベルで状態把握と配慮を
学級の子供の間に安心して自己を表現する関係が育っていない、支持的な雰囲気に乏しい、一部の子供が排除されていることなどが明らかになった場合は、自殺予防教育導入前に学級の実態に応じた心理教育も必要です。ハイリスクの子供に対しては、単に授業から外して情報から隔離するのではなく、面談を含む丁寧な対応が必要となります。
自殺予防教育実施に向けての下地づくり(出典:「子供に伝えたい自殺予防」文部科学省)
(4)実施後の留意点
授業実施後は、相談したいことの有無、相談しようと思う相手、授業への感想などを尋ねるアンケートを実施するとよいです。事後アンケートにおいて危険性が感じられたり、困りごとを表明している子供には、早い段階で個別に話を聴きます。時間があれば、全員と話ができるとさらによいです。専門的な支援が必要な場合は、スクールカウンセラーにつなぐだけでなく、状況によっては保護者へ伝え、専門機関へつなぐことも検討します。
☆もし、子供の自殺が実際に起こったら…(遺族・子供たちへの対応)
自殺は生徒指導上の様々な問題行動に比べて数こそ少ないですが、起こってしまうと、その家族はもとより、学校全体も大きく混乱し、多くの人々の心に深刻な影響を与えます。
自殺事案発生後は、遺族だけでなく、児童生徒や保護者、地域、警察等の関係機関、場合によってはマスコミなどに対し、速やかに対応していく必要があります。そのため、管理職を中心にして、組織的に対応していくことが大切です。
県教育委員会では、要請により、当該校にスクールカウンセラースーパーバイザー(SV)を派遣します。SVは、児童生徒へ与える影響について助言するとともに、児童生徒への伝え方や保護者対応、心のケアなど、今後学校としてどうしていくことがよいのかを教職員と一緒に検討していきます。
(1)子供を亡くした家族との関わり
子供を亡くした家族は混乱状態の中で学校との連絡をとることになります。家族の様子に配慮し、電話でなく、家庭訪問等をして家族に寄り添いながら話を伺います。亡くなったことを校内の児童生徒にどう伝えるか、通夜・告別式などへの参列が可能かなど、家族の意向を尋ね、それに沿った対応をしていきます。在校生や保護者に伝える内容は文書にして、目を通してもらうようにします。
(2)関係の深い子供への対応
親しかった友人、遺書の宛名の人や携帯電話、メール等の最後の交信者には、警察がすぐに事情確認を行います。保護者の承諾を得てから行いますが、その際、保護者や学校職員が同席あるいは待機することを申し出て、子供の激しい動揺を支えることができるとよいです。
その後、学校で児童生徒に対し、亡くなった子の直前の様子や交友関係を尋ねる場合、事実を知らされた衝撃を受けていることを理解し、分かる範囲内の話でよいと説明し、話してくれたことに謝意を示すとともに、今後心配なことがあればいつでも話を聞くことを伝えます。それと同時に、情報の錯綜を防ぐため、根拠のない情報に振り回されたり、自分から流したりすることがないよう伝えます。
(3)子供たちの心と体に現れる反応
身近に衝撃的な出来事が起こると、子供の心と体には次のような反応がしばしば現れます。
- 自分を責める
- 他人を責める
- 死への恐怖感
- 集中できない
- 一人でいることを怖がる
- まるで何もなかったかのように元気にふるまう
- 反抗的な態度をとる
- 食欲不振、不眠、頭痛、腹痛や下痢等
これらの反応は、時間の経過や子供の年齢によっても、現れ方が異なっています。これらの反応は誰にでも起こり得る自然な反応なので異常ととらえず、子供たちに安心感を与えながら回復に努めていきます。
特に自殺した子供と関係が深い、現場を目撃した、元々自殺に関するリスクがある、日頃からストレスにさらされている等に該当する子供についてはリストアップをし、スクールカウンセラーなどと協議して、より丁寧に対応するなどの配慮が必要です。
(4)子供たちへ出来事を伝える際の配慮
心や体に反応が現れるまでの時間は個々によって異なり、中には1週間以上経ってから友達の死を受け入れ、反応を示す子供もいます。そのため、伝えた後も学校と家庭が連携を取りながら子供の様子を見守り、気になる点があれば校内で協議していくことが大事です。出来事を伝える際は、前述のとおり遺族の意向が最優先されます。遺族に伝える内容を確認していただいてから子供たちに伝えることになりますが、事実を知った後の反応に対応できるよう、伝える手順や方法、場所、時間などに配慮が必要です。さらに、心配な子供については保護者に連絡をし、迎えに来てもらう、帰宅後の様子を注意深く見てもらうなどの協力を求めます。死別を体験したときは、一般的には「事実の否認→怒り→絶望→受容」という死別を受け入れる過程をたどると言われていますが、いつまでも否認が続く、悲しみが長期化し感情の揺れが大きい、などで日常生活に支障をきたす場合は、医療機関の受診も視野に入れる必要があります。
(5)クラスでの伝え方
事実を伝える(知)
パニックの伝染を防ぐ意味でも、全校集会等では校長は概要のみを伝えます。その後、学級で子供に向き合いながら、あらかじめ職員間で確認しておいた伝える内容の基本形に基づいて事実を伝えていきます。
感情を表現する(情)
事実を伝える中で、子供たちから様々な感情が出てきます。複雑な気持ちを自然に表現できるようにしてあげるとともに、黙っていることも悲しみの一つの表現として認めてあげてください。教師が自分の気持ちを否認すると、子供も自分の気持ちを抑えてしまいます。悲しい時は泣いてもよいことを伝えてください。泣き続ける場合は、途中で休憩を入れます。
これからどうするかを話す(意)
事実を伝え、少し感情を表現したところで、徐々にこれからのことも話します。まず、自分がとてもつらくなったときに誰に相談するのかを話してみます。友達、家族、教師のほかに、カウンセリングや相談先のことを教えてあげてください。また、自分が知っていることや気になることがあれば、それを信頼できる大人に伝えることも一つの方法だと伝えてください。次に、とてもつらい気持ちの友達がいたら、どんな配慮ができるかを尋ねてみるなどしてください。
参考資料(必ず一読してください。)
- 「教師が知っておきたい子どもの自殺予防」マニュアル【平成21年3月文部科学省】

- 子どもの自殺が起きたときの緊急対応の手引き【平成22年3月文部科学省】

- 子供に伝えたい自殺予防(学校における自殺予防教育導入の手引き)【平成26年7月文部科学省】

- 「いじめゼロ」へ!(千葉県版教職員向けいじめ防止指導資料集)【平成27年2月千葉県教育委員会】
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
