ここから本文です。
子どもの意識・実態調査について「子どもの権利・参画のための研究会」による調査実施結果(概要版)
1.調査の目的
千葉県では、平成17年3月、「子どもは地域の宝、すべての子どもと子育て家庭の育ちを地域のみんなで支える」として、千葉県次世代育成支援行動計画を発表しました。
そこには、これまでの子育て支援策に加えて、「子どもと若者の権利・社会参画の推進」・「若者の自立・就労支援」・「子育て世帯の経済的負担の軽減」・「仕事と子育てが両立する働き方の実現」など幅広い施策が盛り込まれています。この計画を推進するために、同年8月末から次世代育成支援行動計画推進作業部会(現次世代育成支援行動計画評価・策定作業部会)が開かれ、その中に、「子どもの権利・参画のための研究会」が置かれました。
研究会では、「子どもが一人の人間としてその意思が最大限に尊重され、自分の意見を表明することができ、自己実現を図ることができるような社会の実現」を目指して、まず、子どもたちが安心してもっといきいきと毎日を過ごせるようにするためには何が必要なのかを、子どもたちと一緒に考えたいと、県内の子どもたちにアンケートを行うこととしました。また、その保護者の皆さんも、子どもたちの現状をどうとらえ、どうしたら良いと考えているのか知るために、本調査を実施しました。
2.調査対象
千葉県内の小学校4年生から高校2年生及びその保護者を対象に5020部を配付しました。回収数は、子ども1,332人、大人1,323人で、回収率は約26%でした。
3.調査時期
一次調査平成19年6月~7月
追加調査平成19年11月~12月
4.調査方法
小学校・中学校及びその保護者については、千葉県子ども会育成連合会の各支部並びに県内小中学校を、高校生及びその保護者については県内の高等学校を通じて調査用紙を配布し、子どもと保護者の回答を返信用封筒に同封し、郵送により回収しました。
5.調査の統計・分析
回収した調査用紙は、子どもの権利・参画のための研究会が集計・分析しました。
6.子どもの権利・参画のための研究会委員名簿
| 氏名 | 所属等 | |
|---|---|---|
| 会長 | 池口 紀夫 | 中核地域生活支援センター夷隅ひなた所長 |
| 池田 徹 | (福)生活クラブ理事長 | |
| 市川 まり子 | ほっとすぺーす主宰 | |
| 岡田 泰子 | (NPO)子ども劇場千葉県センター理事長 | |
| 甲斐 久美子 | (NPO)東金山武子育て支援センター理事長 | |
| 副会長 | 黒木 裕子 | (NPO)佐倉こどもステーション理事長 |
| 佐藤 浩子 | CAPぽけっと CAPスペシャリスト |
平成17年8月~平成20年3月
7.調査結果概要
問1.子どもの生活意識について
問1-1-1 (子ども)あなたは毎日の生活が楽しいですか。
図1-1-1( 1 楽しい 2 まあまあ楽しい 3 どちらともいえない 4 あまりたのしくない 5 楽しくない)
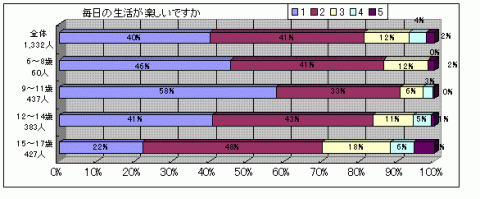
問1-1-2(大人)あなたのお子さんは「毎日の生活が楽しいと思っている」と思いますか。
図1-1-2(1 楽しいと思っていると思う 2 まあまあ楽しいと思っていると思う 3 どちらともいえない 4 あまり楽しくないと思っていると思う 5 楽しくないと思っていると思う 6 わからない)
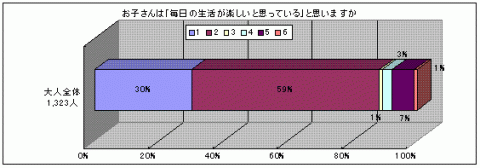
問1-2-1 (子ども)あなたが学校生活の中で楽しいと感じるのはどんなときですか。(いくつでも)
図1-2-1(1 友達や先生と仲良くしているとき 2 授業がよくわかるとき 3 授業の内容や先生の話しが、興味が持てておもしろいとき 4 自分の意見や考えを発表して、先生や友だちに認められたりほめられたりしたとき 5 クラスや学校行事・活動などで自分の意見が生かされたとき 6 委員会活動などで、他のクラスや他の学年の人たちといっしょに活動するとき 7 休み時間や放課後に、友だちとしゃべったり遊んだりするとき 8 部活動(クラブ活動)をしているとき 9 テストで良い成績が取れたとき 10 その他 11 楽しいと感じることはない)
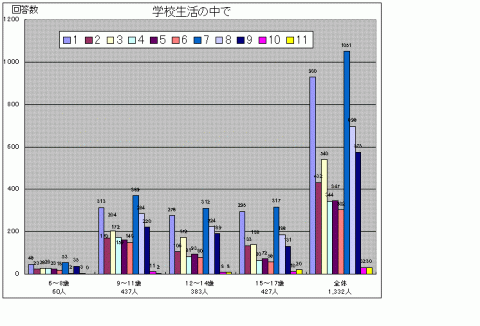
問1-3-1(子ども)あなたはつらい気持ちになったことはありますか。(いくつでも)
図1-3-1(1 親や家族と仲良くなくて、つらい気持ちになった 2 友だちや先生と仲良くなくて、つらい気持ちになった 3 授業がよくわからなくて、つらい気持ちになった 4 自分の意見が聞いてもらえずに、つらい気持ちになった 5 部活動(クラブ活動)の中で練習などがきびしくて、つらい気持ちになった 6 テストの点数が悪くて、つらい気持ちになった 7 受験や進路のことでうまくいかずに、つらい気持ちになった 8 その他の理由で、つらい気持ちになった 9 つらい気持ちになったことはない)
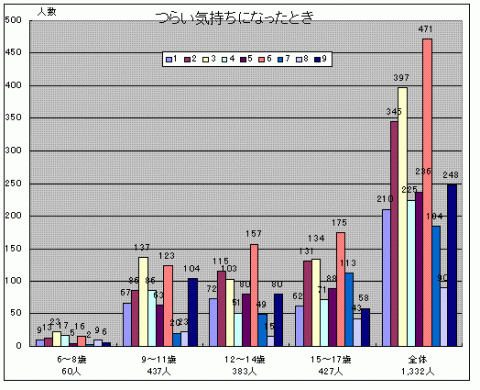
問1-4-1 (子ども)あなたはつらい気持ちになったとき、あなたはどうしようと思いましたか。(いくつでも)
図1-4-1(1 相手の人と話し合って、何とかしようと思った 2 誰かに相談して、助けてもらおうと思った 3 自分は悪くないから、気にしなかった 4 自分がしっかりしなきゃ、と思った 5 自分が悪いと思って、がまんした 6 相談してもしかたないから、相談しなかった 7 生きているのがいやになった 8 その他)
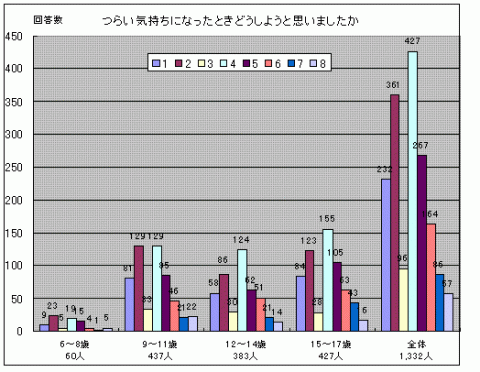
問2.子どもの相談相手・居場所について
問2-1-1 (子ども)あなたは困ったこと心配なことがあったときに一番よく相談するのは誰ですか。(一人選んでください)
図2-1-1 (1 親(ア 父 イ 母) 2 兄弟姉妹 3 祖父母や親戚の人(おじいさん・おばあさん・おじさん・おばさん・いとこなど) 4 友だち 5 担任の先生 6 保健室の先生 7 それ以外の先生 8 スクール・カウンセラー 9 塾の先生・スポーツクラブのコーチ 10 電話相談の人 11 メールやチャットなどの仲間 12 その他 13 相談する人はいない)
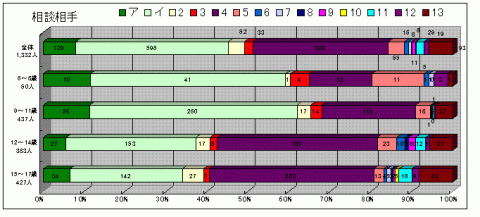
問2-1-2 (大人)あなたは、お子さんが心配事や悩み事があったときに誰に一番相談していると思いますか。(一人選んでください)
図2-1-2 (1 親(ア 父 イ 母) 2 兄弟姉妹 3 祖父母や親戚の人 4 友だち 5 担任の先生 6 保健室の先生 7 それ以外の先生 8 スクール・カウンセラー 9 塾の先生・スポーツクラブのコーチ 10 電話相談の人 11 メールやチャットなどの仲間 12 その他 13 相談する人はいない 14 わからない)
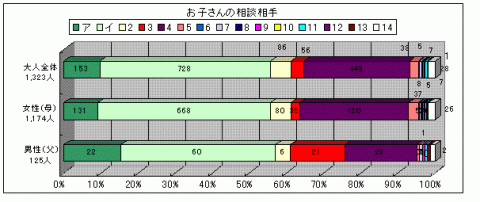
問3.子どもに対するいじめ、暴力(なぐる・けるなど)について
問3-1-1 (子ども)あなたは、つぎのようないじめにあったことはありますか。(いくつでも)
図3-1-1(1 無視 2 仲間はずれ 3 物を隠された 4 暴力を受けた 5 悪口を言われた6 落書きをされた 7 その他 8 いじめられたことはない)
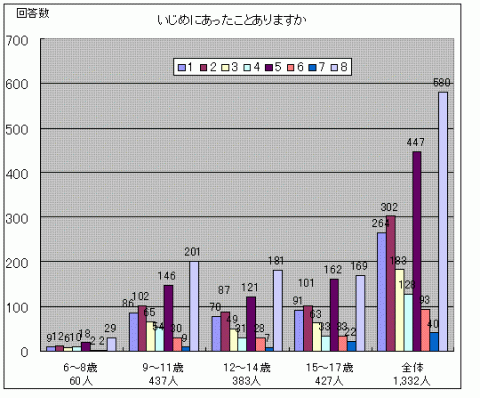
問3-2-1 (いじめられた経験がある子どもに質問)いじめられたとき一番助けてくれたのは誰ですか。(一人選んでください)
図3-2-1(1 親(ア 父 イ 母) 2 兄弟姉妹 3 祖父母や親戚の人 4 友だち 5 担任の先生 6 保健室の先生 7 それ以外の先生 8 スクール・カウンセラー 9 塾の先生・スポーツクラブのコーチ 10 電話相談の人 11 メールやチャットなどの仲間 12 その他 13 相談する人はいない)
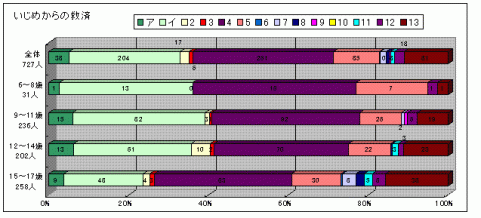
問3-3-1 (子ども)あなたには今までに、おとなから暴力(なぐる・けるなど)を受けたことがありますか。
図3-3-1 (1 よくあった 2 ときどきあった 3 なかった)
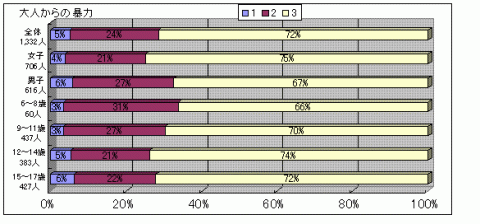
問3-3-2 (大人)あなたは、今までにお子さんに(なぐる・けるなど)を加えたことがありますか。
図3-3-2(1 よくあった 2 ときどきあった 3 なかった)
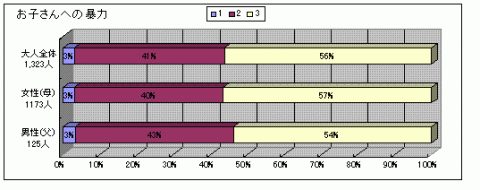
問3-4-1 (暴力をうけたことがある子どもへ質問)暴力を受けたときにどのように感じましたか。
図3-4-1(1 悲しくなった 2 自分がよくないことをしたと思った 3 自分のためにしてくれていると感じた 4 腹がたった 5 その他)
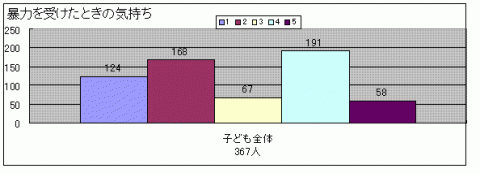
問4.子どもの意見表明と親の傾聴姿勢について
問4-1-1 (子ども)あなたは、家庭や学校で言いたいことをがまんすることがありますか。
図4-1-1(1 よくある 2 たまにある 3 ない)
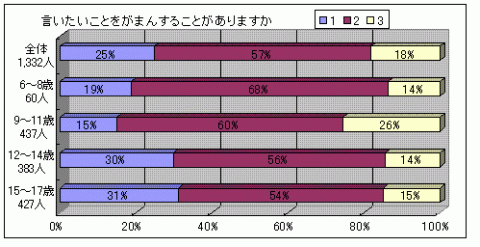
問4-1-2(大人)あなたは、ふだんお子さんの意見を聞くようにしていますか。
図4-1-2 (1 よく聞いている 2 少しは聞いている 3 聞いてない)
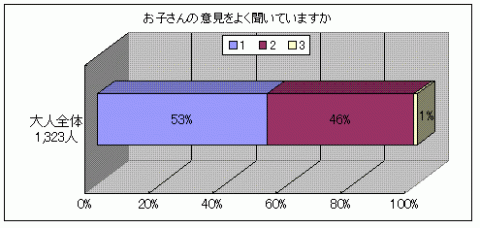
問4-2-1 (子ども)家庭や学校であなたの意見は大切にされていますか。
図4-2-1(1 大切にされている 2 ある程度大切にされている 3 大切にされていない)
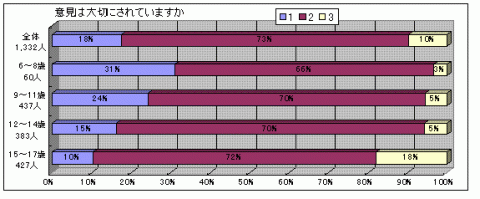
問4-2-2 (大人)あなたは、ふだんお子さんの意見を大切にしていますか。
図4-2-2 (1 大切にしている 2 ある程度大切にしている 3 大切にしていない)
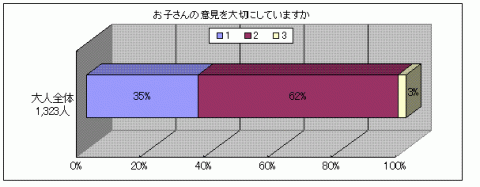
問5.子どもの自尊感情と自己肯定感について
問5-1-1 (子ども)あなたは自分が大切にされていると感じますか。
図5-1-1 (1 いつも感じている 2 ときどき感じる 3 あまり感じることはない 4 まったく感じない 5 わからない)
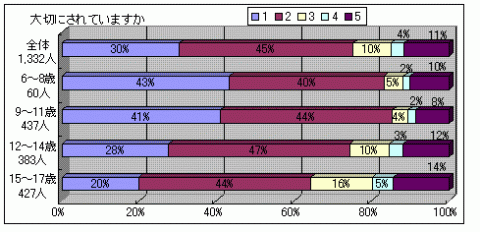
問5-2-1 (子ども)あなたは自分のことが好きですか。
図5-2-1 (1 好き 2 まあまあ好き 3 あまり好きではない 4 好きではない 5 わからない)
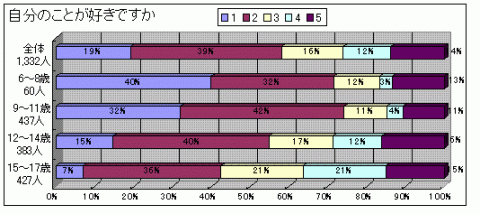
問5-2-2(大人)あなたのお子さんは「自分自身のことが好きだと感じている」と思いますか。
図5-2-2 (1 好きだと思う 2 まあまあ好きだと思う 3 あまり好きではないと思う 4 好きではないと思う 5 わからない)
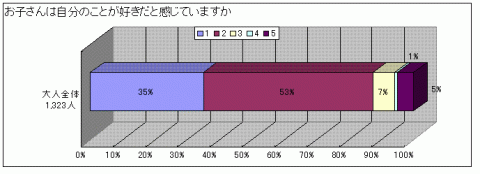
問6.「子どもの権利条約」の認知度について
問6-1-1 (子ども)あなたは、子どもの権利について国際的な条約があることを知っていますか。
図6-1-1 (1 よく知っている 2 聞いたことがある 3 知らない(聞いたことがない)
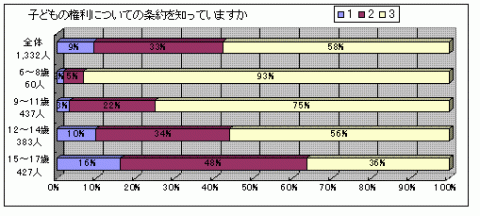
問6-1-2 (大人)あなたは、子どもの権利について国際的な条約があることを知っていますか。
図6-1-2 (1 よく知っている 2 聞いたことがある 3 知らない(聞いたことがない))
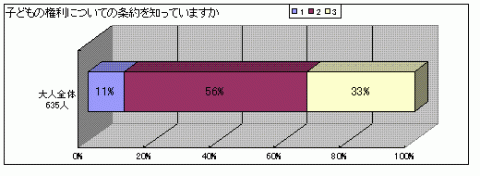
問6-2-2 (大人)あなたは、「子どもの権利」についてどう考えますか。(いくつでも)
図6-2-2 (1 すべての子どもに等しく「子どもの権利」があるということを、こどもたちにきちんと伝えなければいけない 2 子どもは、自分自身の「こどもの権利」が尊重されることにより、他の人の権利を尊重することや「人権」の大切さを学ぶべきである 3 まず、おとなが、一人ひとりの「子どもの権利」を守ることが大切である 4 子どもに権利ばかり教えるとわがままになるので、同時に義務や責任も教えないといけない 5 義務を果たせない子どもに権利はないと思う 6 その他 7 わからない)
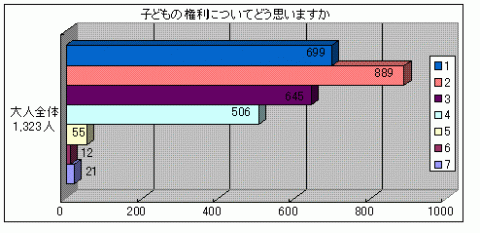
8.各調査項目間の関係について
(1) いじめと自尊感情(自己肯定感)の関係
「いじめにあったことがあると回答した子ども」→「自分のことが好き」に対する回答
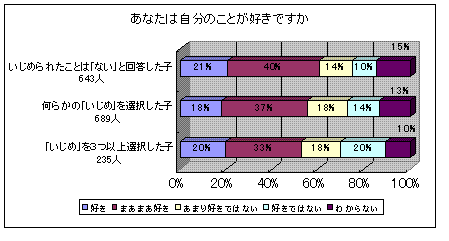
「いじめにあったことがあると回答した子ども」→「大切にされている」に対する回答
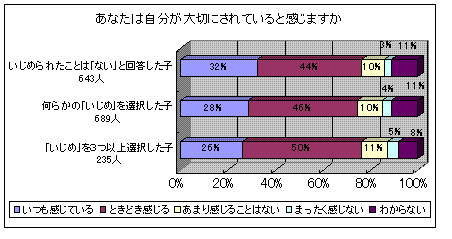
(2) 暴力と自尊感情(自己肯定感)の関係
「大人から暴力を受けたこがあると回答した子ども」→「自分のことが好き」に対する回答
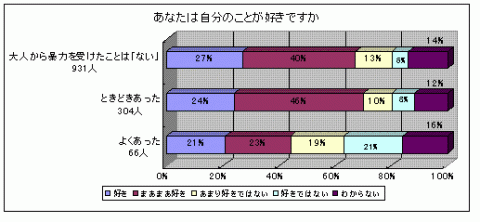
「大人から暴力を受けたことがあると回答した子ども」→「大切にされている」に対する回答
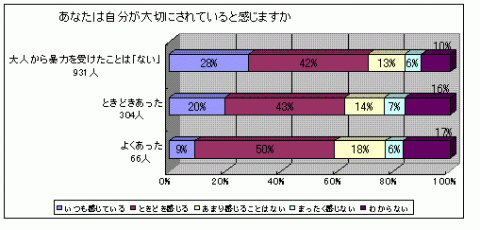
(3) 意見表明と自尊感情(自己肯定感)の関係
「言いたいことをがまんすることがあると回答した子ども」→「自分のことが好き」に対する回答
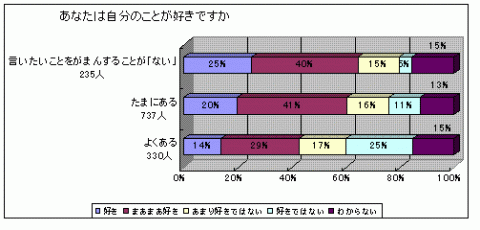
「言いたいことをがまんすることがあると回答した子ども」→「大切にされている」に対する回答
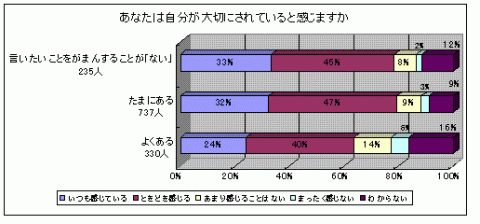
(4) 子どもの権利条約の認知度と人権意識の関係
「子どもの権利条約を知っていると回答した子ども」→「いじめを受けたことがある」に対する回答
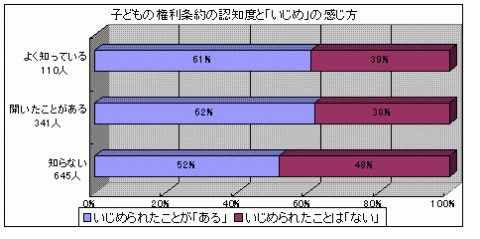
「子どもの権利条約を知っていると回答した子ども」→「意見が大切にされている」に対する回答
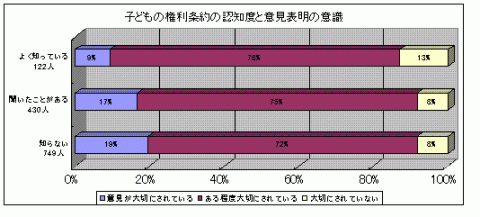
「子どもの権利条約を知っていると回答した子ども」→「暴力を受けたことがある」に対する回答
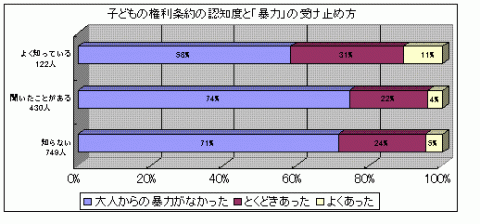
「子どもの権利条約を知っていると回答した大人」→「暴力を加えたことがある」に対する回答
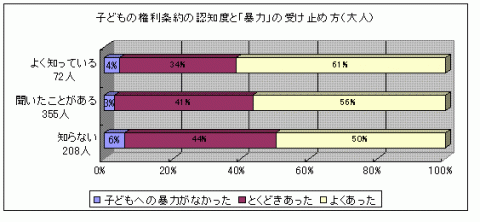
「子どもの権利条約を知っていると回答した大人」→「子どもの意見を大切にしている」に対する回答
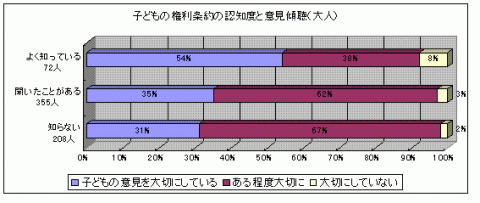
9.見えてきたこと
以下、回答結果から浮かび上がってきた主な点についてまとめてみた。
- 千葉県の8割程度の子どもたちは日々の生活を楽しく過ごしており、また、7割程度の子どもたちが概ね「大切にされている」と感じている。これは多くの子どもたちが良好な気持ちで日々を過ごしており、守られていることを実感していることを示している。
- しかしながらその意識状況を詳細に見ていくと、様々な課題も見えてくる。
- 子どもたちを苦しめている「いじめ」についての質問では、「いじめられたことはない」と答えた 子どもは全体の44%に過ぎなかった。
- また、いじめられたことがある子どもは「自分が大切にされている」という意識が低下し、「自分のことを好きではない」という回答が増えている。このことは「いじめ」が、子どもたちの自己肯定感を損なうことや、安心感を損なうことにつながっていることを示している。
- 子どもの人権に関わる重要な事実の一つが大人からの暴力である。約50% の大人が「ときどき」を含め、子どもへ暴力を加えたと回答している。
- 一方で、暴力を受けたことへの子どもの意識は、「悲しくなったり」「腹が立った」が多い。また、自分がよくない」や「自分のためにしてくれている」との回答も多く、これを大人がどう受け止めるべきか、議論が必要であろう。
- 大人からの暴力が「よくあった」子は、「自分が好き」と答える比率が半数以下となり、「大切にされている」と感じる比率も大きく減少している。
- これらの事実は暴力を受けたことが、子どもたちの自己肯定感や自尊感情を損ねる結果になっていることを示している。つまり、子どもたちが成長し自立してくために必須な栄養源が損なわれているということではないか。
- いじめを受けた時に、誰が助けになったかについては「友だち」が比較的多い。これは「いじめ問題の乗り越え」にとって大事な視点を示唆するものではないか。
- 一方で、年齢が上がるにつれ助けてくれる人が「誰もいない」と言う回答が増えていることは憂慮すべき点である。
- 楽しいと感じるときについては、「友達や先生と仲良くしているとき」がどの年齢においても回答率が高いが、「授業や成績に関すること」や委員会活動などの自治的な活動に参加することを楽しいと感じる子どもが年齢が上がるとともに少なくなっていく。
一方で、授業や成績・受験のことを「つらい」と答える回答が多く、小学校高学年では「授業がわからなくて」との回答が最も多くなる。
また、重要な事実は「生きていくのがいやになった」と回答した子どもが6%いるということであり、「つらいときに相談しても仕方がない」と思っている子どもが12%いるということである。これらは大人が考えなければならない重要な課題であろう。 - 子どもの成長にとって、自分の考えを言えることとしっかりと聞いてもらうことはとても大事なことである。
- 「言いたいことをがまんするときがあるか」について、「よくある」「たまにある」が子どもたちの約8割に達している。
- 中高生では「がまん」している率が高くなる。思春期には「自分の考えを」主張していくことが自然であることを考えると、この結果は自我の成長にとっての問題を提起していると思われる。
- 同じ設問に対する大人の回答は、子どもの意見を「聞いている」との回答が多く、子どもの意識との間に「ずれ」が見られる。
- 自分の意見が「大切にされている」と感じている子どもは多いが、年齢が上がるにつれその割合は減少している。
- 親は子ども以上に「意見を大切にしている」と思っており、双方の意識に「ずれ」が見られる。
- 言いたいことをがまんすることが「よくある」と答えた子どもは「自分のことが好き」の比率が下がり、「大切にされている」といつも感じるという比率も少なくなる。このことも、自分の意見が言えないことや聞いてもらえないことが子どもの自尊感情や自己肯定感という「成長の栄養源」に大きな影響となっていることを示している。
- 「つらい」時や「困った」時に相談できる人がいることは子どもにとっての「安心感」につながる大事なことである。
- 相談する相手は全体に母親が多いが、年齢が上がるにつれて、「友だち」が増えてくる。このことは、子どもが親離れをして、子ども同志の社会が大きな意味を持っていくという自然な傾向を示していると言えよう。
- 親は自分自身が子どもにとっての「よき相談相手」と思っている率が子どもの回答より高く、子どもの意識との「ずれ」が見られる。
- 自分のことが「好きかどうか」を問うた設問に対しては、「自分のことが好きだ」との答えが、年齢とともに少なくなり、「好きではない」との回答が増加している。思春期に入る子どもたちが自分を肯定できなくなることは考えなければならない問題であろう。
なお、親の回答では、9割近くが「子どもは自分のことを好き(まあまあを含めて)と思っているだろう」との結果が出ており、ここでも子どもの意識とは「ずれ」が見られる。 - 子どもの権利に関する条約を知っているかどうかを問うた設問については年齢が高くなるにつれ「知っている」が増えてはいる。
しかし、「よく知っている」が高校生段階でも16%であり、中学生段階では半数以上がその存在を「知らない」と答えている。
大人でも「知らない」が3分の1あり、「よく知っている」は高校生より少ない。国が批准した条約の周知について、その方策を考えていく必要があると思える。 - 「子どもの権利」の内容についての大人の回答では、考え方が相反する結果が出ており、今後、子ども大人双方でよく議論していく必要を感じる。
全体に子どもの条約を知っている子どもや大人は、人権に対する意識が高いと思われる結果が出ている。今後の具体策の検討に反映させていく必要を感じる。
10.子どもの実態・意識調査
千葉県子どもの実態・意識調査結果(PDF:15,821KB)
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
